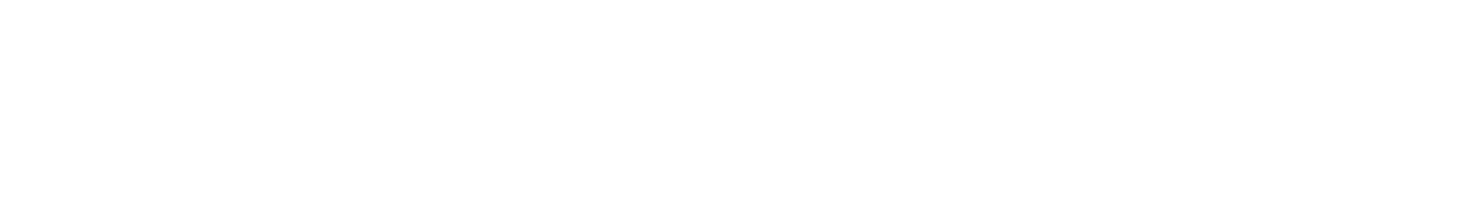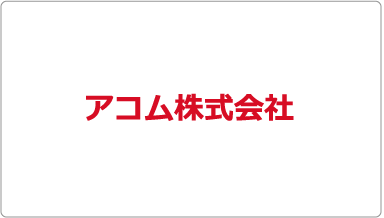相続が開始したときの葬儀の手続きの流れ<川西・伊丹・宝塚>
2017/11/26
相続が発生したときの葬儀などの手続きの流れ
エンディングノートや終活でお葬式の形態も決めておかれる方も多いと思います。ここでは基本的なところになりますが、葬儀などの流れを解説したいと思います。
医師の診断
自宅など病院以外で亡くなられたときは、医師の手配が必要です。病死かどうか医師の診察のうえ、死亡診断書をお願いする必要があります。これを書いてもらうことで、死亡届の提出が可能となります。
葬儀会社の手配
どなたを喪主にするか決めて、葬儀会社の手配をすることが喪主の最初の仕事と言えます。遺言書で喪主が決めてあることも多いため、公正証書遺言の場合は、直ちに遺言書の確認が必要となります。自筆証書遺言の場合は、開封は厳禁です。葬儀方法も故人が生前に葬儀会社や葬儀の形式など取り決めていたら、それに基づいて葬儀を進めていくことになりますが、最近は特に決めていないという場合も多く、ご予算に応じて家族葬や直葬などが増えています。
最近は、故人(もしくは喪主の方)の想いを届けるような葬儀も多いことから、依頼先の葬儀会社の選択も重要なキーワードとなっています。「保険の窓口」と同じく葬儀の窓口というべきところで、まずは相談してみて、近隣でご希望に沿う会社があるかどうか探してみるのが良いでしょう。遺言書の作成などの際に当職にご相談頂ければ、相談先もご紹介しています。
葬儀の日程は、暦の友引を外して、葬儀会社と僧侶の方の日程を調整して決めます。
故人の関係者等に日程を案内する必要があります。家族葬が一般的になってきていますが、市長や大会社の社長などVIPの方が参列する場合には、代表焼香などお焼香の順番や止め焼香、そして弔辞も事前にお願いしておく必要があります。喪主のご挨拶や香典返しにお布施も含め、一つ一つ決めていくには、時間的余裕が無い中で大変な準備となります。病気や怪我で大変な状態で亡くなられた方であれば、お通夜の前に納棺師にエンバーミングをお願いして、お顔をきれいにすることも一つの儀式として行われています。
お通夜、お葬式を済ませたら、火葬場に向かい、終わったら、初七日の読経も行って、まずは、一区切りです。
その後、四九日までの間、宗派によっては毎週、読経をお願いする必要もあります。四九日が終わるとお香典を頂いていたら、満中陰の返しもする必要があります。
通常、百日(か1周忌)で納骨となりますので、お墓の準備もあり、1周忌か3回忌までは、何かと重要なことが続きます。ここで、墓石は墓地(寺)に指定されていることが通常で、墓石だけは、ネットで探す際には指定業者かどうか確認が必要です。お墓についても永大供養や一心寺のように合葬などで行うなどお墓の在り方も様々です。お墓をどのようにするといったことも遺言書で書いておかれる方もいます。
----------------------------------------------------------------------
司法書士 三宅総合事務所
〒666-0035
住所:兵庫県川西市花屋敷1丁目10番3号
電話番号 :072-755-0377
的確な相続・遺産整理を川西市で
----------------------------------------------------------------------